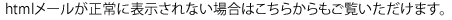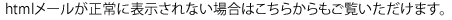|

ロボットに癒やされる日?
阿部又一郎
2022年5月に、有名な米国の実業家が日本の出生率の減少を憂慮する発言をSNS上で発信した際、それが日本社会を構成する人たちに向けたこころからの共感(エンパシー)であると、一体どれくらい感じ取れただろう。「科学的」データで予測された少子高齢化と労働力不足を懸念するSNS上の言葉に心揺さぶられるうちに、すでに私たちは高性能次世代型人型ロボットの売り込みが周到に準備された、薄暗い欲望の河に飲み込まれている。
前回書いたコラム「双極性と境界性をめぐって―翻訳作業を支えた異国滞在」(星和書店 こころのマガジン Vol.161, 2016)に続いて、今回は『ロボットに愛される日―AI時代のメンタルヘルス』(セルジュ・ティスロン著、2022年)を翻訳出版したおかげで再び執筆の機会をいただけた。すでに何度か来日講演し、著書もいくつか紹介されている原著者の略歴は、訳者あとがき他の繰り返しになるので割愛する。原著は人型ロボット「ペッパー(Pepper)」が華々しく社交デビューした翌年(2015年)に出版されたが、残念ながらペッパーの方は、邦訳出版前すでに日本のメディアから静かに退場していた。
ロボットは、今も昔も研究者の探求心を刺激する。19世紀フランスのアンドレイド(アンドロイド)小説『未来のイヴ』(ヴィリエ・ド・リラダン著)の主人公の名もエジソンであった1)。コンピューター誕生直後の1950年代、知識工学が創設された1980年代に続いて、2010年代以降は第三次AIブームと呼ばれている。ロボティクス研究者の石黒浩氏が、自身に酷似したジェミノイド(Geminoid)を発表したのは2006年であった。2022年上半期に、フランス国立自然史博物館の協力のもと日本科学未来館で開催されていた特別展「きみとロボット ニンゲンッテ、ナンダ?」2)は盛況であったときく。
ロボットとの関係性は、臨床や実践に取り組む人間の思考も刺激する。最近、オートポイエーシスの哲学者と、フロイディアンの精神分析家が対話していたが、こちらは同じ「いしぐろ」でも、家族で長崎から英国に戦後移住した作家カズオ・イシグロの『クララとお日さま』で、弱さの引き受けがテーマのひとつとされる3)。日々の暮らしのなかで、ロボットの表象を目にしない日は少ないくらいで、最近では、どう見ても令和版「ドラえもん」としてキャラ設定されている少年漫画誌の連載作品のTVアニメ化が決定されていた 4)。筆者自身は、コロナ禍の期間中、半ば自発的に病院宿直ロボットと化していた(隷従はしていない)が、休憩室のテレビのスクリーン上(ブラウン管とはもう言わないか)で再放映された、宮崎駿の描く人間-ロボットのインタラクションの光景に、しばしば癒やされていた。
日本のロボット文化は、やはり他所からみると特異的なものに映るようだ。オイルショックが起きる前に提唱された「不気味の谷」現象は、今世紀に入って世界的に知られるようになった5)。西欧において、機械(ロボット)に仕事を奪われるという不安、ロボットが人間に反乱を起こし、逆に支配しようとするディストピア的恐怖を描いた作品は、SFに限らず、かなり普遍的にみられる。いまや日本を代表する漫画家である、ゆうきまさみの初期作品に、人型ロボット(いやアンドロイドか)をテーマにした学園パロディがある6)。作品は、あまりに精密に人間に似せて作られた人型ロボット=アンドロイドが、人並みに抜けていることをこれ以上なく描写した80年代後半の傑作。「人並みに愛されるほど、よくできた高機能人型ロボット」という、日本の戦後ロボットマンガにほぼ共通してみられる発想は、西洋の伝統的な技術論には、ほとんどみられなかったようである7)。
ここから先の、ロボットと日本的心性というややこしい考察には入り込まないが、ロボットについて書き出すと、どうもノスタルジックな調子を帯びてくる。最新テクノロジーのなかに、アナログ的な懐かしさが喚起される仕組みなのだろうか。西垣通氏によると、情報科学のパイオニアたちに通底するのは、マッドサイエンティストのような冷たさではなくて、一種の熱いナルシシズムであるという8)。自己のアバター(分身)である自動機械人形のなかでは、自己と他者が無限に入れ子になっている。その眼差しを通して自己を、生物を、社会を、世界を眺めたいという欲望こそ、じつはエロティックな時代精神の底流をなすものであるという指摘から、すでに30年近く経過している。
ここ数年、精神医学関連の諸学会でも、ロボットを媒介にした支援介入法をテーマにシンポジウムが組まれるようになった。こうしたシンポでは、最新テクノロジーを搭載したAIロボットの利用を通じた、遠隔精神医療のポテンシャルと、将来的に早期介入も含めた精神医療改革にもつながる可能性という、明るい未来が(いくらかの留保とともに)語られる。特に、対象によっては、人間のセラピストが関わるよりもロボット相手の方が、とりわけ恥にまつわる感情や親密な内面を自己開示しやすいことがエビデンスとして示されてきている。ロボットが将来、人間にとってかわることは制度的にありえないにしても、メンタルヘルス系専門職の負担軽減(または代理)が大いに期待されている。果たして将来、心理療法家の「ラッダイト運動」は起こるだろうか?
近い将来、メンタルクリニックを開業するとなると(筆者は今のところ予定ないが)、治療環境としてどんな設定を考えるだろう。最新の診断基準がインストールされて、用語も適宜アップデートしつつ、うつと不安に対する簡単なソクラテス式問答と、共感的受け答え(まさにワイゼンバウムの制作したELIZA令和版!)まで実装された卓上小型汎用ロボットが開発されれば、従来の電子カルテや古典的な寝椅子の代わりに導入を検討するだろうか。ドラえもんのひみつ道具「あんきパン」の開発を待つよりも、はるかに実現性は高そうだが。懸念されるのは、デジタルツールを通じて生活習慣が管理されると、かえって生の感覚や主観的満足感が減じうる可能性と、ロボットがアップデートされている限り、データ情報がつねに外部にアクセスされうる危険性、すなわち秘密情報の取り扱いという倫理的課題であろう。
臨床のスーパービジョンも、いずれは遠隔支援型ロボットで代用されるだろうか。確かに、すでに一部は、オンライン研修で十分に可能である。筆者の周りには、老境に達していても、なお一層の診断面接の達人芸を垣間見せたり、農園や庭仕事に出かけて土いじりの癒やし効果を再発見して心躍らせる先達の臨床医がいる。いつの日か、彼(彼女)らの所作やコトバを記憶貯蔵したり、機械学習したロボットが登場したら、そこにかつての馴染みの患者さんたちは来院し続けるだろうか。それは、ないだろう。診察室内に残された写真やモノに包含された記憶が想起されたり、新たな別の治療関係のなかで再現されることはあっても。そもそも、ロボットは人間のセラピストのように、話を聴(聞)いてもらった体験をもつのだろうか。「誰かの話を聞くためには、別の特別な誰かに話を聴いてもらっている」経験が、心理(精神)療法の前提であるならば9)、ロボット開発者もセラピストの訓練を受ける必要があるのだろうか? 今後、ロボットと人間の関係を考えていくには、さまざまなプロジェクションのはたらきも大事な課題のひとつになるだろう。
今回の翻訳で最後まで悩まされたのが、第7章「神の似姿、預言者的イメージ」であった。推敲を続けていて、学生時代に受講した教養課程の美術史の授業で、『フランケンシュタイン』の著者メアリー・シェリーの想像力をめぐる逸話を紹介してくれた故・若桑みどり先生(1935〜2007)の教えを思い出した。校正が佳境に入る2020年のステイホーム期間中、時短営業中の書店内で先生の名著が新・新装版で復刊されていたのを見出して10)、懐かしさで励まされた。稀有なる存在であった先生に感謝!――そんな追想の機会を、困難な状況下で誰にでもやさしく提供しうるAIロボットならば、未来のアバター共生社会も悪くはないけれど。
参考
1)特集21世紀に『未来のイヴ』を読む.ふらんす2022年9月号,白水社.
2) https://kimirobo.exhibit.jp
3)河本英夫:創発と危機のデッサン-新たな知と経験のフィールドワーク.学芸みらい社,240-241,2022.
4)TVアニメ「僕とロボコ」公式サイト: https://boku-to-roboco.com
5)森 政弘:不気味の谷.エナジー誌,エッソ・スタンダード石油,Vol.7,No.4,33-35,1970.
6)ゆうきまさみ:究極超人あ〜る. 少年サンデーコミックス,小学館,1986〜87.
7)フレデリック・カプラン. 西垣通(監修),西兼志 (訳):ロボットは友だちになれるか―日本人と機械のふしぎな関係.NTT出版,2011.
8)西垣通:デジタル・ナルシス: 情報科学パイオニアたちの欲望.岩波現代文庫,2008.
9)東畑開人:聞く技術 聞いてもらう技術.ちくま新書,2022.
10)若桑みどり:薔薇のイコノロジー(新・新装版).青土社,2020.
阿部又一郎(あべ ゆういちろう)
1999年千葉大学医学部卒業,精神科医。2008年フランス政府給費生としてエスキロール病院,ASM13ほかにて臨床研修。医学博士。2014年,東京医科歯科大学精神行動医科学助教を経て,現在,伊敷病院勤務,東洋大学大学院非常勤講師。訳書に『ロボットに愛される日―AI時代のメンタルヘルス』(星和書店刊)などがある。
|
|